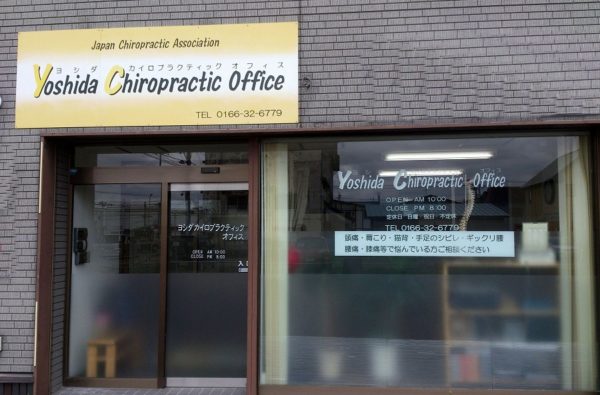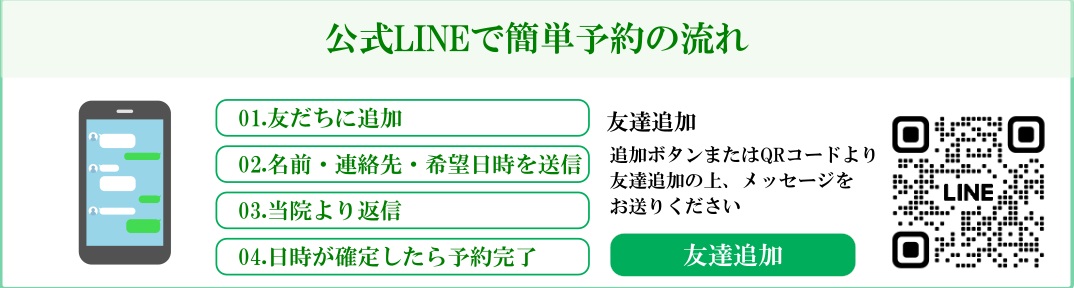当整体院では日々肩こりや腰痛などのお客様に対し施術をする傍ら、最近では学生の部活動などの支援(テーピングや筋トレ指導など)なども行っています。
しかしどこか痛くし病院などに行ってこの症状は「〇〇ですね」と何やら難しい診断名を告げられます。
しかしスポーツ障害などの診断名って難しく一般の方には理解しにくいのが本音ではないでしょうか?
そこで病院で診断されるスポーツ障害の代表的な症状を少しでも分かり易く解説をしていきたいと思います。
スポーツ障害とは?
最近では「スポーツ障害」という言葉自体大分認識されてきたので1度は聞いたことがある言葉かも知れませんが、あえて「スポーツ障害とは何か」をお話させていただきます。
まず、一般的なスポーツ障害の例を挙げていきたいかと思います。
主なスポーツ障害
- シンスプリント
- アキレス腱炎症
- 足首などの捻挫
- 肉離れ
- 腰痛
- ランナー腱炎
これらの症状が最も一般的なスポーツ障害の例になりますが、スポーツをされている方なら皆さん1度くらいは経験をされている症状かと思います。
勿論上記以外にももっともっと沢山の症状がございますが、例を挙げるとキリがないのでこのくらいにしときます。
それではなぜ上記の様なケガなどが起こるのでしょうか?その原因についてお話させていただきます。
-

参考スポーツ障害とスポーツ外傷の違いについて|子どもの小さなSOSを見逃さないで
子どもがスポーツ系の部活に入っていると、完全にケガを予防するというのは難しいことかと思います。 しかし練習前にしっかりと身体のケアをすることで、ある程度はケガを予防するこが可能です。 またスポーツ時の ...
続きを見る
スポーツ障害の主な原因は身体への疲労(負荷)が溜まることによっておこる
シンスプリントや肉離れなどの症状を引き起こす主な原因には、練習中や試合中に身体へ加えられる負荷が強すぎたり疲労が溜まることで起こしやすくなります。
練習や試合後にしっかりと身体のケアを行えばこれらスポーツ障害を予防するのに効果的ではありますが、ハッキリ言って申し訳ないですが練習後のケア不足なことは否めません。
試合に勝ちたいなどの理由により子供たちは一生懸命練習には取り組みますが、練習後のケアについてはどこか適当に行っている感が非常に強く感じられます。
なので最近ではこれら「足首の捻挫」や「アキレス腱炎」・「腰痛」などといった症状を訴える子供が増えているかと思います。
メモ
足首の捻挫を繰り返す子どもは、足の脛の筋肉(前脛骨筋/ぜんけいこつきん)が張っている特徴があります。
この前脛骨筋は脛の外側から土踏辺りに付着している筋肉で「つま先を上げたり」「足首を内側に捻る」際に動き筋肉なので、捻挫癖があるという方はこの筋肉をしっかりとストレッチをし筋肉の柔軟性を回復させると捻挫が起こりづらくなります。
スポーツ障害(ケガ)によりパフォーマンスの低下は起こり得る
そしてこれら症状(スポーツ障害)が起こると、スポーツ中のパフォーマンスの低下(全力でプレーが出来なくなる)がみられます。
またケガなどの影響により、身体が元の正常な状態に戻るまでにはある程度期間(時間)がかかります。
そしてこれらスポーツ障害の特徴と致しまして筋・腱・軟骨といった筋骨格系が影響を受けやすく、痛みや腫れといった症状が現れ走ったり跳んだりといった運動の妨げになります。
せっかくその「競技で上手くなりたい」や「試合などで勝ちたい」と思って一生懸命に練習をしても、スポーツ障害により練習を休まなければならない状況になってしまう意味がありません。
また、スポーツ障害により練習を休んでしまうと元の身体に戻すにも休んでいた倍の時間が必要だと言われているので、出来ることならスポーツ障害などを引き起こさず日々練習をおこないたいですよね。
スポーツ障害は大きく分けて2種類


それと先ほどから全てのケガなどに対してスポーツ障害と一括りでお話していますが、実はスポーツ障害は大きく分けて2種類に分類することが出来ます。
そしてこのスポーツ障害にも「自分で防げるスポーツ障害」と「自分では防ぎきれないスポーツ障害」があることを覚えておきましょう。
それでは2通りのスポーツ障害についてお話させていただきます。
コンタクトスポーツに多い「急性損傷」や「外傷」


先ず一つ目は、急性損傷や外傷による損傷です。
これらの損傷は、ラグビーやサッカーなど相手と接触することがあるスポーツ(コンタクトスポーツ)に多くみられます。
外傷の特徴は、捻挫や打撲・肉離れ・じん帯損傷などといった筋や腱の損傷が多くコンタクトスポーツではある程度防ぐのが難しい症状となります。
しかしある程度防ぐことは難しくとも極力それら損傷が起きない様にするためにも、普段から「各関節の可動域を広げる」や「コンタクトに負けない体つくり(筋力アップ)」をして行くことが大事になります。
練習のし過ぎで起こるやすくなる「慢性損傷」や「障害」


先ほどの急性損傷や外傷といった突発的起こる損傷に対し、長時間の練習などにより使い過ぎ(オーバーユース)が原因で起こる症状が「慢性損傷」や「障害」と呼ばれるスポーツ障害があります。
これら「慢性損傷」や「障害」はオーバーユースが原因で身体の一部に摩耗や微細な断裂が生じて起こりやすくなると言われています。
また、障害の特徴としては腱鞘炎や滑液包炎・疲労骨折などといった症状が多く、同じ動作を繰り返し行うスポーツに多くみられる症状です。
長距離ランナー(ランナーズニー)やテニス(テニス肘)や野球(野球肘)といったスポーツをされている方に多い障害です。
スポーツ障害は原因を把握することが大事です
スポーツ障害を起こす原因には、正しいフォームを身に付けず練習を繰り返し行った結果や適正な道具(靴など)を使わなかったから起きてしまう場合があり、スポーツ障害を起こしてしまう原因は必ずしも1つでは無く多岐にわたる場合が多いです。
また、コンタクトスポーツに多い外傷も体つくりや正しいフォームを身に付けることで受傷するリスクを軽減させることが出来ます。
それでは、スポーツ障害を起こす原因をいくつか挙げていきたいかと思います。
ウォーミングアップの不足
スポーツをする際の準備不足により筋肉などの反応が遅れやすくなり、肉離れなどを起こしやすくなります。
またウォーミングアップは静的なストレッチではなく動的なストレッチの方が効果的です。
過度に負荷を掛け過ぎる
身体の能力に対し過度な負荷を掛けすぎた場合、筋断裂や腱断裂などが起こる。
特に試合中など普段より負荷が上がることによって障害を引き起こします。
筋力不足や筋のアンバランス
体力の低下や筋力の低下そして前後左右の筋肉のアンバランスが影響を及ぼし、ある一定の筋肉に負荷がかかり過ぎて障害を引き起こします。
練習中のフォームなどを見直しによりある程度一定の筋肉に負荷がかかることを防げます。
オーバートレーニング
練習のし過ぎにより身体に常に負荷がかかり慢性的な障害のリスクが増大します。
練習後や試合後のケア不足が原因になり易いので、子どもたちにはケアの必要性を十分理解させてあげることが大事です。
柔軟性の不足
筋肉や関節が固いと身体の可動域にも制限がかかり、日々の練習で負荷がかかりやすくなり慢性障害を引き起こしやすくなります。
練習後のケアに加えご自宅などでもストレッチなどを行うようにすることが大事です。
関節弛緩性
柔軟性の不足とは逆に関節が緩すぎて安定性の欠如がおこり怪我を起こしやすくなる。
関節が緩い状態の方はインナーマッスルなどを強化をすることで障害を予防することが出来ます。
インナーマッスルを鍛えるにはゴムチューブなどを使用したトレーニングが効果的です。
障害の再発
同じ箇所を何度も何度も怪我などをしていると患部は弱体化を招きその他の部位にまで影響を与えてしまうようになります。
痛みが治まったら障害が完治したのではなく、何度も同じ障害を引き起こす場合にはしっかりと完治するまで身体を休ませることも大事になります。
スポンサーリンク
この様にスポーツ障害には様々な原因がありますが、普段の練習や試合後の身体のケアで十分防ぐことが可能です。
先ほども申しましたが1度スポーツ障害を起こしてしまうと元の状態へ戻るにはある程度期間が必要になります。
ですので極力練習や試合中にスポーツ障害を引き起こさない為にも、しかりとした身体作りと身体のケアを心掛けるようにしましょう。
特に新たなスポーツ始められる方などは筋肉のバランスが悪かったり、正しいフォームで練習を行わないことが多い傾向があります。
新たなスポーツを始めようとされている方は、初めは無理をせずじっくり身体作りをすることをおすすめします。
注意ポイント
特に中学生や高校生などは各々の身体の状態(身長や体重など)が違ってきますので、子どもたちを指導されるコーチ陣などは子どもの身体の状態にあった練習強度やケアの方法などを指導するようにすることが大事かと思います。
子どもの身体作りのお手伝いもしています
元々私自身も子どもの頃から様々なスポーツをしていて、身体を動かすことが大好きです。
そして整体師となり身体についての知識が付いたことにより、自分の健康の為の身体作りやスポーツをされている子ども達の身体作りなどのお手伝いもしています。
整体院と聞くと肩こりや腰痛などの時に行くとお考えの方も多いかも知れませんが、当整体院ではスポーツ障害時など少しでも早くケガの回復が出来るお手伝いもしています。
また当整体院ではケガに対しての施術後には再度ケガが起こりにくい様にするための身体作りのご指導なども行っています。
お子さんが部活動などで何度も同じケガなどをする場合は、身体の使い方に難があるかも知れません。
当整体院ではその様にケガがしやすい身体の使い方をしているお子さんには身体の使い方なども指導をしていますので、子どもが何度も同じケガをするとと言う場合は1度当整体院へご相談を!
旭川市で身体のケアのことなら旭川市の整体院ヨシダカイロプラクティックにご相談を